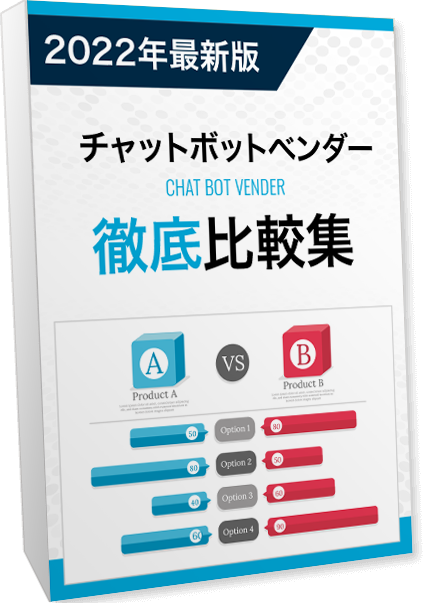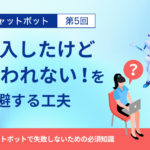第2回:チャットボット運用失敗する原因はこれ!|チャットボットで失敗しないための必須知識
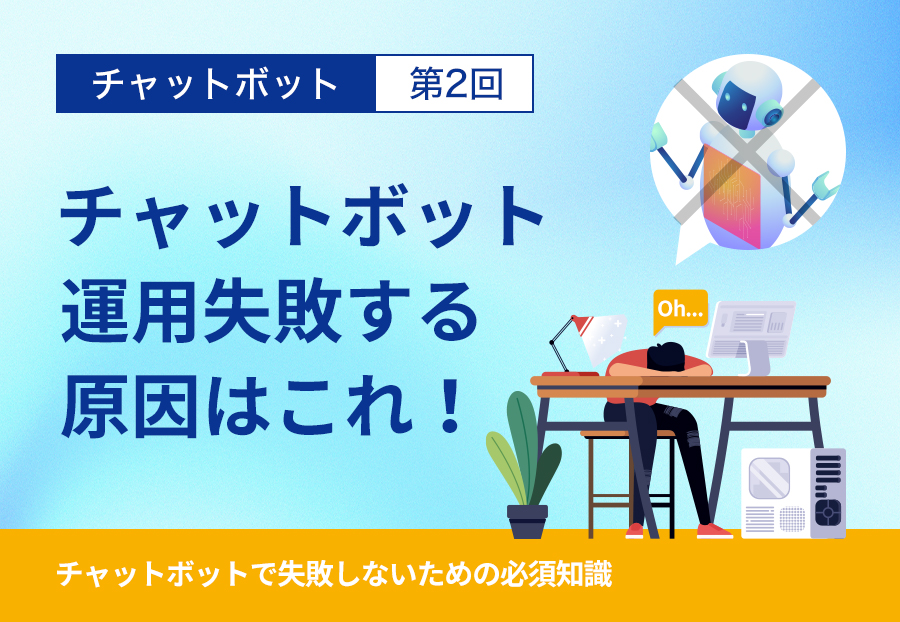
最終更新日:2022年7月28日
この記事シリーズでは『AIチャットボットの導入で失敗しないための必須知識』と称して、 これからチャットボットの導入を検討されている方に必ず知っておいて欲しい知識をご紹介いたします。(全5回)
チャットボットについて詳しくない方でもわかりやすいよう、前提となる知識からご紹介いたしますので、ぜひ順を追って5回まで閲覧いただければと思います!
- 第1回:FAQシステムとAIチャットボットの使い分け方
- 第2回:AIチャットボット導入の主な失敗要因はこれ
- 第3回:AIチャットボットは自動で賢くなりません!担当者がハマる落とし穴
- 第4回:AIチャットボット導入後のメンテナンス作業はこんなに大変です汗
- 第5回:導入したけど使われない!を回避する9つの工夫
さて、第2回では「どうしてチャットボットの運用に失敗してしまうのか、その原因を知りたい」という方に向け、これまでサイシードが試行錯誤を繰り返す中で蓄積されたデータをもとに、失敗事例についてご紹介いたします。
この記事の目次
よくある失敗1, チャットボットを導入しても社員が使ってくれない
これは最も多い失敗理由だと言っても過言ではありません。チャットボットを導入したのに、社員がチャットボットを利用してくれないというものです。
たいていの場合、次のような流れがあって社員がチャットボットを使用しなくなります。
- 導入目的の周知や運用体制の構築など前準備をないがしろにしたまま、チャットボットを導入する
- 社員が興味本位でチャットボットを利用してみる
- チャットボットが十分に教育されていないため、ロクな回答を返さない
- 社員が「使えないツールだな」と評価する
- 誰も使わなくなる(いくら改善しても、そもそも使われない)
そうならないためにも、サイシードでは導入前のFAQ整備段階から運用開始後の改善段階まで、専任のカスタマーサクセスが併走できるよう準備しています。
どんな目的で導入するにしろ、チャットボットの運用を成功させるためには、導入前の準備が最重要項目となります。
【大手建設業界経営企画室 K課長】
社員からの情シスへの問い合わせ対応を削減するために、システム操作やPCトラブルに回答してくれるAIチャットボットを導入しました。そのベンダーの営業担当者からは『最初は精度が低くても大丈夫です。使っていくうちに精度が高くなりますから安心してください!』と言われていたので、100件程度のFAQでリリースしました。
当初は、社員たちも面白がって様々な質問をしてくれ、1日100件程度使われましたが、導入後1ヶ月も経過すると、1日10件程度とほとんど使われなくなりました。これでは学習しようにも、データが全然足りません。
ユーザーの入れ替わりが少ない社内ヘルプデスクでAIチャットボットを導入する場合、社員は1,2回使ってみて『使えないな』と思われた場合、それ以降は使ってくれなくなるということがよくわかりました。確かに私自身ですら『結局答えにたどりつかないんだよな』と思っていたので、AIチャットボットに聞くことなく電話をしてしまっています。
最低契約期間は3年間なので、今後どう立て直していくか気が重いです。
よくある失敗2:削減できた業務量より、チャットボット運用の業務量が多くなってしまった
次に、チャットボット導入による業務削減量よりも、チャットボット運用のための業務量のほうが多くなってしまい、結果的に業務量が増えてしまった、という失敗理由があります。
多くの担当者様が勘違いしていることでもありますが、チャットボットの運用は片手間でできるようなものではありません。日々の利用データから適切な改善個所を特定し、定期的にメンテナンスを行う必要があるのです。
【大手通信会社情報システム部 Y担当課長】
「AIチャットボットを導入すれば、私の業務はかなり楽になるものだと思っていました。実際、AIの初期学習とFAQの作成も依頼したので割とスムーズに導入することができ、問い合わせ数も20%ほど減少しています。しかし、AIチャットボット導入後も想定していた以上にやることが多かったです。
・具体的には、実際に使われたログを見ながら、同じ質問内容の新しい表現を、FAQに紐付ける
・「回答がわかりにくい」という評価を受けたFAQの回答をわかりやすく変更
・FAQに登録されていない質問文は、新たにその回答も作成して登録
という業務が新たに発生してきました。しかもその業務は、導入担当の私が引き続き行うことになったので、導入後も3ヶ月程度はかなりいっぱいいっぱいでした。
現在は、派遣社員の業務を調整してもらいこれらの業務を割り当てることができましたが、情シス担当者が少ない企業の場合は予め運用担当者を付けれるよう根回ししておく必要がありますね。」
よくある失敗3:社員にチャットボットの存在や利便性を認知されなかった
3つ目の失敗理由は、社員にチャットボットの存在自体を認知されなかったというものです。
【大手製薬会社 情報システム部 C部長】
「突貫工事で社内向けに導入してしまったこともあり、社員にFAQシステムの存在や利便性が認知されず、利用率は全然上がりませんでしたね。
3ヶ月後に社員に『FAQシステム導入のお知らせ』をメールで一斉配信しましたが、日々のメールに埋もれてしまったのか特に効果はありませんでした。
何とかしなきゃとは思っていましたが、何から手を付ければいいかもわからなかったですし、僕自身が非常に多忙な時期だったのと、部署の他のメンバーもたくさん業務を抱えていたので、結局全然テコ入れが出来ませんでした。もはやFAQシステムの解約期日が来るのを静かに待っているといった感じです。
とりあえず導入すれば何とかなるかなーとは思っていたのですが、甘かったです。
AIチャットボットやAI搭載のFAQシステムはここ数年注目をされ始め、多くの企業で急速に導入が進んでいるので、メリットばかりにフォーカスがされがちです。
しかし、実際には上記の失敗事例のように、人による業務が多く発生します。
以上で紹介したほかにも、チャットボットの運用には様々な課題が付きまといます。これまで多くの企業が失敗してきた背景には、こうした課題をクリアできない現実があり、これからチャットボットの導入を検討しているのであれば必ず回答を用意しておきたい部分でもあります。
AI搭載型チャットボットを提供しているサイシードでは、チャットボットの運用にあまりリソースを割けない方や、運用ノウハウに自信がない企業に対してカスタマーサクセスプランをご用意しています。
導入初期のヒアリング・FAQ構築段階から、導入後の効果改善段階までしっかり併走させていただきますので、この機会にぜひご検討ください。
第2回:チャットボットで失敗しないための必須知識まとめ
本記事では、チャットボットを導入した企業がどうして失敗してしまうのか?よくある失敗理由を3つご紹介いたしました。
これからチャットボットを導入するのであれば、もちろん最終的にサイシードをお選びいただかなくとも、カスタマーサクセスプラン(運用コンサルティング)が付随したパッケージを選択することを強くお勧めします。
具体的にどのような準備が必要なのか、どのような運用改善を行っていくのか知りたい方は、第3回以降の記事もご参照ください!
チャットボット30社の徹底比較レポート
計15項目から100点満点で評価・比較いただけます