スマホアプリを利用したチャットボットサービスが増えた理由とは?事例と導入のポイントも解説!

最終更新日:2022年7月5日
このブログはAIを活用したチャットボット『sAI Chat』を提供する、株式会社サイシードが作成しています。
最新の事例や企業での活用方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
人間に代わって、AIを搭載した自動応答システムがユーザーと会話をする「チャットボット(chatbot)」。企業の抱える慢性的な人手不足の問題を解決するソリューションとして、チャットボットは大きな注目を浴びています。
最近では、PCよりもスマホでネットをアクセスするユーザーが増えているので、企業もPCではなくLINEなどのスマホアプリにチャットボットを組み込むサービスも増えてきました。
今回の記事では、アプリを利用したチャットボットサービスに焦点を当て、急成長の理由や導入事例、そして実際に開発・導入を進めるためのポイントついてご紹介します!
また、記事の最後では「『チャットボットベンダー』徹底比較集」をプレゼントいたしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!
▼関連記事:
この記事の目次
アプリ型チャットボットサービスが増えた背景
顧客対応の人手不足を解消するため、Webサイトに設置するWebチャットやiPhoneに搭載されている音声認識アシスタントSiriなどのチャットボットを活用したサービスは多様化してきています。その中でも最近著しい成長を遂げているのが、LINEやFacebookなどのメッセージングアプリを利用したチャットボットサービスです。
アプリ型チャットボットサービスが増加している背景にある3つの要因についてご説明していきます。
1 開発プラットフォームのオープン化
アプリの開発プラットフォームのオープン化(=規格を公開すること)が進んだことが挙げられます。その先駆けとして2016年にFacebookが自社のメッセージングアプリのオープン化を行いました。それに続く形でLINEやTwitter、Microsoftなども次々とオープンプラットフォームを発表しました。このようにプラットフォームのオープン化が進んだことにより、外部企業がチャットボットを利用したサービスを自由に提供できるようになり、導入企業からのアクセスが簡便化されたと言えます。
2 スマートフォンの爆発的な普及
周りを見渡せばほとんどの人がスマートフォンを使っているほど、現代社会を生きる人にとって必要不可欠なものとなったスマートフォン。その普及に伴い、スマホアプリやWebサービスのユーザー数が増えた一方で、スマートフォンの利便性からユーザーからの問い合わせも増加傾向にあります。ユーザーの抱えるトラブルを解決し顧客満足度を向上させるため、スマートフォンから気軽に問い合わせできるサポート体制を構築することが多くの企業で急務となっていることが、導入需要が増加した要因の一つと言えます。
3 チャット型コミュニケーションの浸透
LINEやMessengerなどのスマホアプリが普及したことにより、誰もが日常的にチャットでやり取りを行なっていますよね。そのため、これらのプラットフォームを活用したチャットボットへの心理的ハードルが下がり、世の中から受け入れられやすくなったと言えます。
調査会社であるReportsnReports社によれば、2016年には7億ドルにとどまっていた世界全体のチャットボットの市場規模は、2021年には31.7億ドルまで膨らむと予想されます。平均成長率は毎年35.2%にも上り、その中でもアプリ型チャットボットサービスは特に伸びていくことが調査結果から読み取れます。
チャットボットを活用したアプリの導入事例
続いて、アプリにチャットボットを組み込んでいる事例を紹介していきます。
事例1:株式会社ユニクロ
大手アパレルメーカーであるユニクロは、2018年7月にチャットボットによる接客機能「UNIQLO IQ」をリリースしました。「あなた専用のお買い物アシスタント」をコンセプトに、自社の公式アプリの一機能として、いつでもどこでも相談ができるサービスです。
「UNIQLO IQ」と会話するだけで、オススメのコーディネートの提案や、トレンド商品の検索、在庫確認まで、買い物における一連の流れをチャットで完結できます。また、カスタマーサポートのオペレーターとのチャット接続も可能です。
開発初期の正答率は約50%でしたが、教師データを地道に作成し、15万人による試験運用を経て、正答率を飛躍的に上げることに成功。正式リリース前の2018年5月の時点で、問い合わせの半数以上がチャット経由に切り替わり電話対応よりも6〜7割の時間で済むことから、前年月と比べて2倍の問い合わせに対応できるようになりました。
事例2:ヤマト運輸株式会社

大手運送会社であるヤマト運輸は、2016年1月よりLINEを利用した通知メッセージのサービスを開始しました。ユーザーはメニュー画面から「再配達依頼」と「集荷依頼」の2つのメイン項目から目的に合わせて選択していくだけです。
はじめはヤマトに会員登録をした約2,000万のユーザーが対象でしたが、2018年10月にはLINEで電話番号が一致したすべてのユーザーがメッセージを受け取れるようになりました。
LINEによるチャットサービスはメールよりも開封率が高く、ユーザーの利便性もアップします。そのため、荷物の受け取りがスムーズになったことで、再配達の件数を削減し、ドライバー負担の軽減に貢献しました。
チャットボットを活用したアプリ導入のポイント

目的達成に適切なアプリやツールを選ぶ
アプリやツール毎にそれぞれメリット・デメリットがあります。
例えば、自社アプリを開発する場合、自由に設計・開発ができるという柔軟性はありますが、ユーザーにどれだけインストールしてもらえるかが大きなポイントとなります。
その反面、メッセージングアプリを活用すれば、新規ユーザーの獲得は容易になりますが、プラットフォームが定める制約により自由な開発は難しくなります。また、メッセージングアプリの中でも、LINEやTwitter、Facebookなど、アプリによって特徴やユーザー属性が異なることから、対象ユーザーにあったプラットフォームを選択する必要があります。
チャットボットを利用する目的を検討し、達成までのシナリオや必要な機能を考えた上で、適切なアプリやツールを選ぶことが大切になります。
企業の目的、ユーザーの特性ごとにどのアプリやメッセージングツールが適しているのかは、下記の記事でより詳しく紹介しています。
チャットボットの管理体制を整備する
チャットボットの開発プラットフォームが次々とオープン化されたことにより、チャットボットを作成するハードルは大きく下がりました。メッセージングアプリを利用する場合は、より開発が容易になってきています。
しかし、チャットボット作成後の教育や管理には、大きな手間と時間がかかることを忘れてはいけません。
AIを実用に耐えうるレベルまで育てるためには、
- 質問文と回答文をセットにした500〜1000程度のFAQ
- その各FAQに対する類似表現
- 広義の質問から回答を特定するためのシナリオ分岐
というような学習材料の作成が必要になります。
正答率が良くなければ、せっかく導入したチャットボットも目的を果たすことはできません。
また、正答率が良くても、使用するユーザーが少なければ意味を成しません。
チャットボットの作成自体は容易になりましたが、作成後に正答率を上げるためのチューニングや、チャットボットを使用してもらうための動線の工夫など、実際の運用を見据えた管理体制を整備することが大切です。
まとめ

こちらのフォームから、「『チャットボットベンダー』徹底比較集」をDLいただけます!
ベンダー比較・検討する際の参考として、ぜひご活用くださいね。
チャットボット30社の徹底比較レポート
計15項目から100点満点で評価・比較いただけます
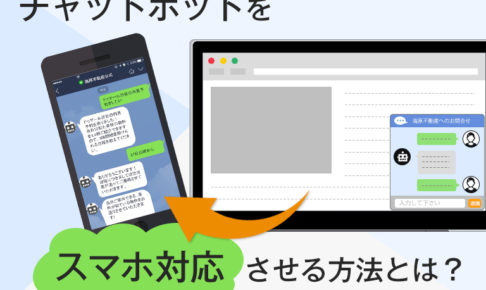
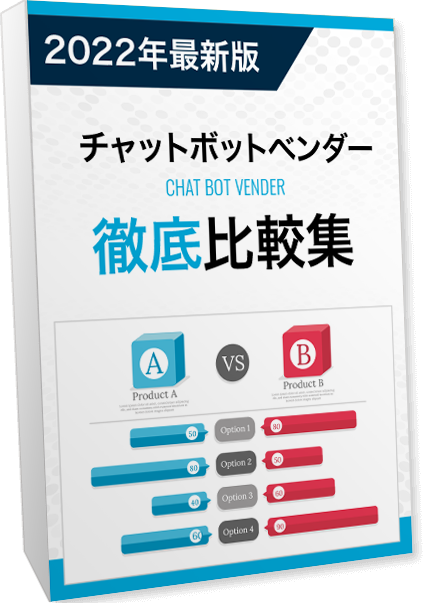

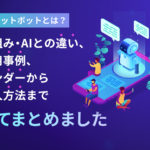



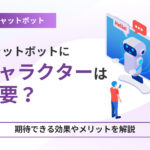
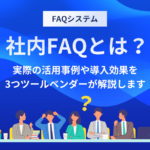
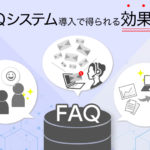

そこで、アプリ導入におけるポイントや注意したい点についてご紹介します。